日本サッカーの躍進を支えた古河電工サッカー部のDNA “プロ”になることを決意した日。

おかだ・たけし/1956年生まれ。大阪府出身。早稲田大を卒業後、1980年に古河電工に入社し、サッカー部に在籍。クレバーなプレースタイルと抜群のリーダーシップで守備の中核として活躍し、1986年のアジアクラブ選手権制覇などに貢献。日本代表としても24試合に出場した。1990年に引退後は古河電工サッカー部コーチを務め、ドイツ留学を経てジェフユナイテッド市原コーチに就任。1995年から日本代表コーチを務めると、1997年には加茂周監督の後任としてチームを史上初のW杯出場に導き、1998年フランスW杯でチームを指揮した。コンサドーレ札幌、横浜F・マリノスでの指揮を経て2007年に再び日本代表監督に就任。2010年南アフリカW杯でチームをベスト16に導くと、2012年には杭州緑城(中国)の監督に就任。2014年11月には四国サッカーリーグ・FC今治の運営会社に出資し、同チームのオーナーに就任。現在は日本サッカー協会副会長、ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ理事など数々の要職を兼任し、日本スポーツ界の顔として各地を飛び回る。
どうしてもマスコミに就職したかった
古河電工に入るつもりは、実はまったくありませんでした。
僕はどうしてもマスコミに就職したかった。だから、実業団からの誘いをすべて断っていました。
当時、マスコミの就職試験は10月の第1週にまとめて行われていました。ところが僕が早稲田大4年時の1979年は、大学選抜が出場するユニバーシアード大会が開催された影響で、大学リーグの最終戦が就職試験と同じ週に行われることになったんです。
古河電工サッカー部から早稲田大学のコーチとして派遣されていた宮本征勝さんには、「就職試験があるから3日間だけ休ませてください」とお願いしました。でも、「サッカーをやめてマスコミで働きたい? そんなに自信があるなら1日だけ休ませてやるから1社に絞れ」と意地悪をされてしまってね(笑)。
言われたとおりに1社に絞りましたよ。テレビ局のTBSに。でも結局、面接でTBSの「B」の意味を聞かれてすぐに「Broadcasting」と答えられなくてね。面接官から「サッカーを続けたほうがいいのでは?」と言われてしまう始末で、結果はもちろん不合格。「落ちたら来てくれ」と言ってくれていた古河電工に筆記試験も面接も受けずに入ることになった——というのが、私が入社することになった理由でした。
最初は本当に大変でした。
僕は学生結婚をしていたから寮ではなく社宅に入れてくださいとお願いしたんだけれど、新入社員を社宅に入れるわけにはいかないと言われて、結局、会社が元役員の経営するアパートを借り上げて、そこを社宅として住むことになりました。
でも、6畳一間の風呂ナシ。奥さんと連れ立って近所の銭湯に行って、小さなちゃぶ台でご飯を食べたら、そこに布団を並べて寝るという生活でした。まるで、かぐや姫※が歌う『神田川』の世界観そのものでしたね。
- ※かぐや姫:南こうせつ、伊勢正三、山田パンダで構成されるフォークバンド
当時、一般社員の給料は残業代で成り立っているようなものだったんだけど、サッカー部員は残業ができないから大変でね。奥さんがアルバイトをしても生活費が足りなかったし、日本代表の遠征に持っていくお小遣いさえなくて苦しい思いをしました。奥さんとよく話しました。「幸せはお金で買える。だから絶対にお金持ちになろう」とね(笑)。
ただ、仕事は本当に楽しかった。僕はいい上司にめぐりあって、若い頃からたくさん仕事をさせてもらいました。
昼休みに地下の食堂でガーッと食べて、そのまま東京駅から横浜に向かってサッカー部の練習をして、練習が終わったらまた丸の内に戻って仕事をする。なんて事もありました。
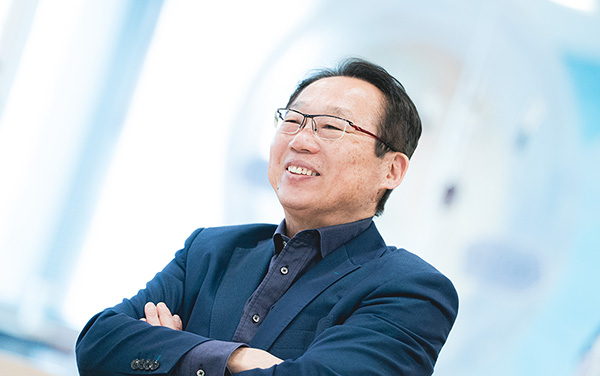
選手として、最高の10年
僕は、ものすごく生意気な選手だったんです。
1984年から監督を務められていた清雲栄純さんはおおらかなところがあって、ミーティングで守備に関する話になると「岡田、お前がやれ」と言って僕に振ることがあった。当時4年目。自分を中心にチームが回っていると、完全にそう思い込んでいました。後に清雲さんの手のひらで泳がされていた事に気づくのですが。
もっとも、ピッチの上では1年目からかなり生意気だったと思います。永井良和さんや奥寺康彦さんのように実績のある選手に対しても、「こっちに動け!」と強い口調で指示を出していましたから。チームメイトにとってはものすごく面倒くさい選手だったと思いますよ。もしも僕自身が監督だったら? そんな選手は絶対に使わないでしょうね(笑)。
1986年のアジア選手権優勝は、やっぱり強く印象に残っていますね。
その前年からものすごく強かったんですよ。金子久、宮内聡、早稲田一男といった若手がどんどん活躍して、永井良和さんや川本治さんのような脂の乗り切ったベテラン選手、僕や吉田弘のような中堅がしっかりとチームを支えていた。本当にいいチームでした。
そこに加えて、1986年秋には西ドイツから奥寺康彦さんが戻ってきた。
やっぱり、奥寺さんはものすごいプレーをされるわけです。格が違う。ただ、だからこその感覚のズレみたいなものもあったし、こちらが遠慮してしまうところもありました。加入直後のリーグ戦では、奥寺さんとチームがうまく噛み合わないという印象でした。だけどやっぱり、アジア王者を懸けたこの大会だけはみんなが「どうしても勝ちたい」と思っていたんですよね。その一体感が奥寺さんとの間にあった壁を取り払ってくれたのだと思います。
年末のサウジアラビアで行われた最終ラウンドは、圧倒的に強いと感じていた遼寧FC(中国)に最終戦で勝てたことが大きかった。試合内容は防戦一方でね。その試合に出場していた中国の選手のひとりとは今でも付き合いがあるけれど、いまだに「俺たちのほうが強かったのに」と言われるくらいですから。
優勝の記念に、会社からは高級酒を1人1本ずつもらいました。当時はそれだけで「やった!」と大騒ぎしていたんだけど、冷静になって考えればうまく丸め込まれちゃったなと思いますね。なんといってもアジア王者ですから。サウジアラビアで開催された大会だったわけだし、優勝賞金だけでもそれなりの金額だったと思いますよ。

選手として過ごした10年間は最高でした。
実業団であっても「俺達はプロだ」なんて言っていたけれど、よくよく考えれば本当に“あまちゃん”だったなと。練習が終わったらみんなで飲みに行って、サッカー談義に花を咲かせて……今になって思えばその辺のサッカー好きとたいして変わらないけれど、それでもみんな、サッカーに対してとにかく真剣だった。
サッカーが好きだったんですよ。将来のことを考えればサッカーをやらないほうがいい時代で、だけど、サッカーが好きだし、古河電工の一員として戦うのが楽しかった。だから、将来の不安なんて考えずに「できるところまでやりたい」と思えたんです。
コーチとしての行き詰まり
引退を決断したのは33歳の時でした。
日本リーグ選抜のキャプテンとしてドイツのバイエルン・ミュンヘンと親善試合をやったのが1990年の1月。木村和司が西ドイツ代表のセンターバック、クラウス・アウゲンターラーの股を抜いてゴールを決めた試合で、1-2で負けたけれど、その内容を絶賛された試合でした。
だけど、僕はひとりでショックを受けていた。次元の違いを感じました。これからどれだけ努力しても、彼らには絶対に追いつけないと。
かつての自分は、「高校に行かず西ドイツに行ってプロを目指したい」と言い張って周りを散々困らせるような中学生でした。
僕があまりにもうるさいものだから、父親がツテをたどって当時サンケイスポーツの運動部長を務められていた賀川浩さん(故人/スポーツライターとして日本サッカー殿堂入り、2015年FIFA会長賞受賞)にお会いすることができました。
賀川さんは、メガネをかけてひょろっとした僕を見るなり「(プロを目指すなんて)やめなさい」と説得されたけど諦めなかった。もっと上手くなっていつかはドイツに行ってプロになるとずっと思っていた。
でも、33歳になってバイエルン・ミュンヘンと向き合った時に「これは絶対にかなわない」と初めて思ったんです。その瞬間に「引退しよう」と決めました。
若い頃から上司に恵まれてたくさん鍛えてもらっていたからこそ、サッカーを辞めて社業に専念しても結果を残す自信がありました。どうせやるなら社長を目指そうと、本気でそう思っていたくらいでした。
でも、そのタイミングで清雲さんが監督を辞めることになってね。後任として監督に就いた川本治さんから「コーチとして支えてくれ」と頼まれて、それを引き受けることにしました。
しかしこれがまったくうまくいかなかった。組織の力も、選手個々の力もまったく引き出せないままコーチを始めて2年で完全に行き詰まってしまった。どうしていいかわからなくなってしまった時に、こう感じたんです。「チームから離れなければいけない」と。

だけど、自分の身分はあくまでサラリーマンでしたから。「充電します」と言う奴に給料を払ってくれる会社なんてあるはずがないわけで。
そう思いながらも、僕はひとまず、人事部にかけあってみることにしました。海外に1年間コーチ留学したい。家族全員を連れて行きたい。会社を辞めてでも行こうと思っている。そう伝えました。辞めて行ける訳がない事をわかっているのにいい会社だった。
そんな普通だったら通りそうもない希望が、会社の全面的なバックアップによって実現することになってしまってね。東西ドイツが統一されたばかりのハンブルクに古河電工の支店を作って、僕がそこの支店長になる。そういう座組で、1年間のドイツ留学が決まりました。
監督の強さは、孤独に勝つこと
ドイツでの経験は話し始めたら2時間かかるから、今回はひとつだけ話しましょうか(笑)。
当時トップレベルのドイツでどんなトレーニングが行われていたのかというと、技術的にも戦術的にも真新しいものは何もなかった。ただ、ひとつだけ僕が強烈に学んだことがあって、それは監督と選手の立場の決定的な違いでした。
例えば、当時の日本代表では集合初日に監督主催の宴会を開催するのが当たり前だった。みんなでどんちゃん騒ぎをして盛り上がって、それによって仲間意識を作るところから始めようとする。
ところが、ドイツにはそんな空気感がまったくない。選手に好かれようと思っている監督はただのひとりも存在しないわけです。
僕はいろいろな苦労の末にハンブルガーSVに受け入れてもらえることになりました。チームにはブルガリア代表として1994年のアメリカ・ワールドカップでも活躍したヨルダン・レチコフという選手がいて、彼はもちろんうまいんだけれど、守備になるとちょっと軽いプレーをするクセがある。
ドイツ人は軽いプレーが嫌いですからね。監督は「レチ! レチ!」と何度も注意していたら、ある日レチコフが「なんで俺ばかり言われなきゃならないんだ!」とキレてしまった。
監督は笛を吹いて選手を集合させると、全員をタッチラインに並べて笛を吹いた。それから延々と連帯責任の罰走が続くわけです。僕は驚いてしまった。「俺たちが中学生の頃にやったやつじゃないか」と。
結局、折れたのはレチコフでした。監督に歩み寄った彼は「これは俺の問題だ。他の選手は帰してやってくれ」と。
監督は選手に対して絶対に容赦しない。一線を越えて馴れ合うようなことは絶対にしない。選手に好かれようなんて思っていたら、勝てるチームを作る指導者にはなれないと思い知らされました。つまり、監督としての強さは孤独に打ち克つこととイコールであると。
その監督はシーズン途中に解任されることになり、彼に誘われて2人でメシを食いに行きました。そこで言われました。「オカ、監督という仕事は孤独なもので、めちゃくちゃ働くか、結果が出せなければ仕事がなくなるかのどちらかだぞ」と。
あの1年間がなかったら、僕の指導者人生は間違いなく成立しなかったでしょう。
僕はドイツで監督と選手の立場の違いを知りました。
「俺がチームを動かしている」と勘違いしていた現役時代の自分に気づくことができたし、だからこそ2年間のコーチ経験が行き詰まったのだと納得できた。
だから、古河電工には感謝しかありません。あの時、会社がハンブルク支店を作るという決断をしてくれなかったら、今の僕は存在しないから。
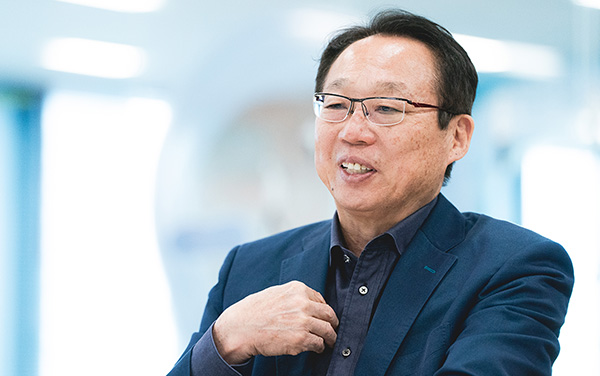
プロになることは“義務”だった
古河電工という会社は、本当に懐が深くて、優しくて、温かくて……一方で、サッカーをやっている自分たちに対しては“ゆるい会社”だったという言い方もできるのかもしれません。自分のためにヨーロッパに支店を作ってもらった僕が言えることじゃないかもしれないけれど(笑)。
僕は上司に恵まれました。
部門長の吉田恒美さんは親身になってサッカー部の面倒を見てくれた人でした。一方、上司の窪田城さんはサッカーに興味がなかった。吉田さんがサッカー部員を引っ張ってくることに対して「俺はイヤなんだ」と口ではいつも言っていたけれど、それでもとことん面倒を見てくれた。「サッカーで食っていくなんてムリなんだから、今のうちにちゃんとやっておけ」と、僕を特別扱いすることなくひとりの同僚として向き合ってくれた。本当はメチャクチャ優しい人で今でも尊敬している。
正直に言うと、最初は「サラリーマンなんて何がおもろいんや」と思っていたんです。ところが、実際にひとりの社会人として仕事と真剣に向き合ってみると、これがもう面白くて仕方がなかった。
僕はお風呂マットの企画管理を担当していました。営業部が取ってきた注文に対して、製造から納品までのあらゆる工程を管理していました。仕事が多岐にわたっていたからこそ、それがビシッとハマって売上が立った時の達成感はものすごく大きかった。それを初めて感じた時に「サッカーと変わらないじゃないか」と気づきました。
- ※「お風呂マット」:AT・機能樹脂事業部門、フォーム製品の一つ。現在は生産終了。
個人としても、チームとしても「こうなりたい」「こうしたい」という目標や夢みたいなものがある。それに向かって試行錯誤しながらチャレンジする。失敗した時の悔しさもあるが、成功した時の喜びもある。難しいことも、うまくいかないこともたくさんあるけれど、自分たちの手掛ける仕事がうまくいったとき、目標を達成した瞬間の喜びは、サッカーで感じるそれとまったく変わらなかった。
当時はいろいろな人から「お風呂マットを売っているのか?」なんてからかわれましたよ。でも、僕自身はお風呂マットを作って売ることにものすごく大きなやり甲斐を感じていた。主力製品のエフレックスを担当したこともあったけれど、お風呂マットにしかないビジネスとしての“現場感”や“臨場感”がたまらなかった。その成功体験があったからこそ、現役を引退した時に真っ先に思い浮かんだのは「社長になってやろう」というモチベーションだった。
もしもあのタイミングで、のちにJリーグが開幕することを知らなかったら、古河電工の社員として社業に専念していたと思います。
- ※エフレックス:古河電工が国内で初めて販売した樹脂製波付ケーブル保護管で、1967年の発売以来、公共工事などで広く採用されている。
現役を引退して、人事部所属のサッカー部コーチという立場も中途半端であまり乗り気じゃなかった。最初は断ろうと思っていたけれど、そう遠くない未来にJリーグがスタートすると聞いて「それならば」と思いました。
もっともそれは「自分もJリーグに関わりたい」というモチベーションではありませんでした。サッカー界が大きな流れを作ろうとしている時に、そのど真ん中にいる自分が「俺は不安だからサラリーマンとして頑張ります」だなんて水を指すようなことはできなかった。Jリーグが開幕しても成功するなんて保証はどこにもなかったから、どちらかというと、サッカーに携わってきた自分としての“義務感”によって指導者の道に入りました。
1年間のドイツ留学を経て帰国した1993年の春、その直後に行われたJリーグの開幕戦を、奥さんと一緒に国立競技場で観ました。
丸1年間日本のサッカーを観ていなかった自分にとっては、驚きでしかなかった。日本リーグ時代、ピッチから家族の顔を確認できるほどガラガラのスタンドしか知らなかった自分にとっては、本当に衝撃的な光景でした。
僕は家族全員に対して「俺もプロ契約したいと思う」と伝えました。いつクビになるかわからないけれど、お前らのことは絶対に食わせていくから心配しないでほしいと。
奥さんにはこう言われましたよ。「いざとなったら、あの6畳一間の生活に戻ればいいじゃない」とね。


 シェア
シェア ツイート
ツイート シェア
シェア